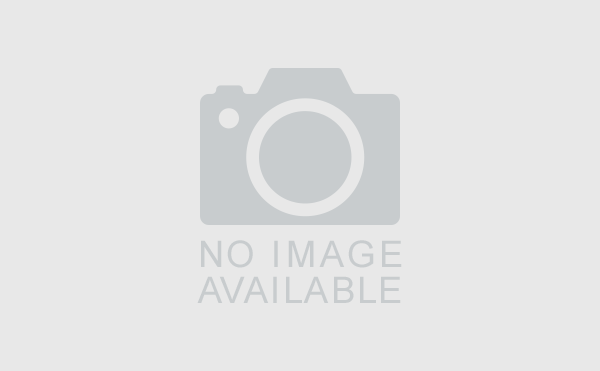松岡まり一般質問報告~2024年第4回定例市議会 その2
今回の質問では、いわゆる主権者教育についていくつか焦点を絞って質問をしました。
1.学校へ行きたくない子どもたちへの支援
(1)「主体的で深い学び」を進めるために
(2)食べる権利をすべての子どもたちへ私は、子どもの友ともだちや友人のこどもたち、様々な場で出会ったこどもたちから、学校について、「学校へ行きたくない」とか、「嫌々行っているよ」とか「でも行かなきゃいけないでしょ」とかよく教えてもらっていました。
子どもたちの声のあちらこちらから、学校が“じぶんのペースで過ごせられない”という切実な思いを聞かせてもらっていると感じています。+++
<質問と答弁の概要>
松岡)10月半ばには「第3次国分寺市教育ビジョン」の原案が出された。この中に「主体的で対話的な深い学びの視点に立った授業改善」
答弁)国の学習指導要領に示される子どもたちの資質・
松岡)授業内容そのものには、どのように取り入れていくか?
答弁)1人1台端末の活用が有効と考えている。
松岡)授業内容以外の場で、取り入れることも必要。学習指導要領には「生きる力 学びの、その先へ」というキャッチフレーズのもと、
教員による、子どもたちのやる気の出る授業を教員たちが見学し、
答弁)やる気を引き出す授業とは、
各学校では、教員同士が授業を見合う授業研究会をしている。
子どもたちの自己肯定感を育むような授業づくりに、
松岡)員の皆さんに、
「あなたはあなたのままでいい」
+++
うーん。。。
私の質問の仕方なのかなあと思うのはもちろんのことですが、どうしても市教委の皆さんのほんとの想いがなかなか汲み取れなくて難しく感じました、市教委の皆さんも現場の教員の皆さんも子どもたちに健やかにすくすくと育ってほしいとの思いは同じはずなのですが。
国分寺市内の子どもたち対象のアンケート結果で「自分のことを大切な存在だと感じているか」という設問で「感じていない」「どちらかといえば感じていない」が小学校3割、中学校2割でした。私には子どもたちの内なる悲鳴が聞こえてきます。子どもたちがよく見る先はわたしたち大人。
わたしたち大人もひとと過剰に比較することをやめて、自分の能力や努力を評価し自分の価値を認めていくことが本当に大切なのです。
アーカイブが配信されています。ぜひ聴いてみてくださいね!